原産地証明とは、輸出または輸入貨物の原産国がどこの国なのかを証明することで、国から指定された原産地証明書の発給機関により証明書類が発給されます。
原産地証明書は、輸出または輸入を行う際に必ず取得しなくてはならない書類ではありませんが、実際に貿易を行う際には取引先と交わす契約内容や取引条件に含まれているケースが多くあります。
そこで今回の物流手帖では、原産地証明書の概要と取得手順するについてご説明していきます。
※本記事は2023年9月時点の情報をもとに作成しています。
原産地証明書とは
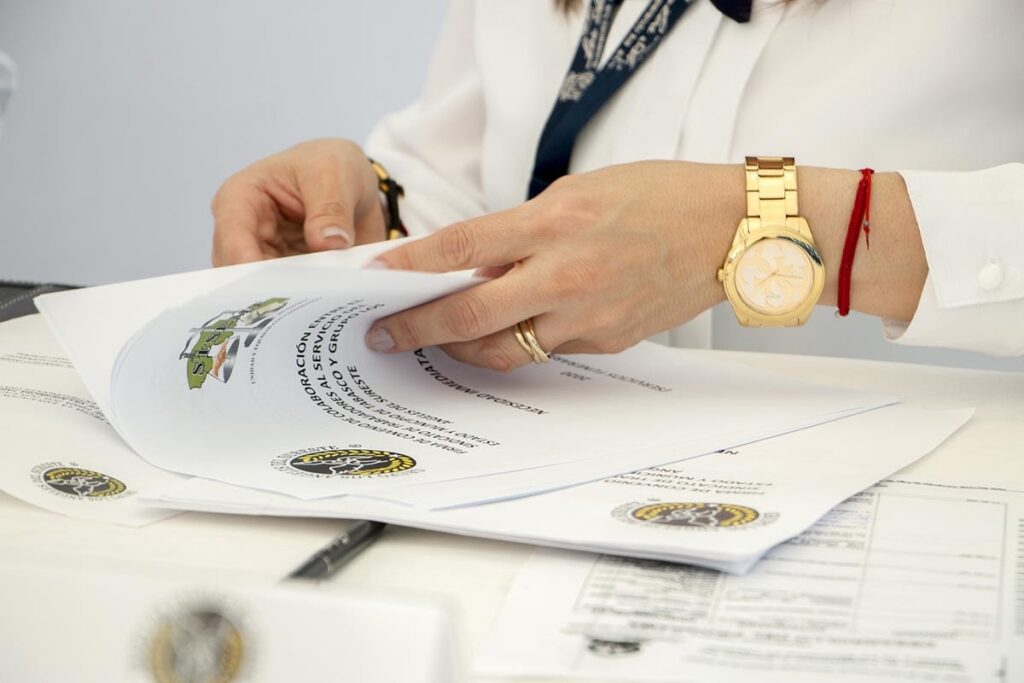
原産地証明書とは、輸入国側の税関で原産地証明が必要な場合に取得する書類のことで、書面には貨物の原産性を保証するための情報が記されています。
原産地証明書は英語で「Certificate of Origin(C/OまたはCOOと略される場合がある)」と表記され、書類の発給はジュネーブ条約に批准した各国のうち、特別に権限を与えられた輸出国側の商工会議所や、商業会議所などの第三者機関によって発給されています。
国によっては、自己申告制度として、輸出者や生産者が自己申告(輸入者が自己申告を行う場合もあります)を行うことで原産地証明書を取得する方法も導入されています。
原産地証明書は、一度取得した書類を何度も使用できるといった類いのものではなく、輸出・輸入を行う『ごと』に書類を発行する必要があり、前回と同一の条件で再び輸出や輸入を行う場合であっても、新たに発行する必要があるので注意しましょう。
また原産地証明書は、書面の名称に「原産地」と記載がありますが、あくまでも原産国を証明する文書となっており、原則として各都道府県名を記載するものではないという点も頭に入れておくと良いでしょう。
(例外として、台湾向けに日本産食品を輸出する場合は都道府県名を記載できる場合もあります。)
原産地証明書の種類
前項でご紹介したように、原産地証明書は国から権限を与えられた第三者機関に発給を依頼する場合と、自己申告により書類を発行する場合(自己申告制度)とがありますが、前者の場合には2種類の証明書があります。
そのうちの一つが「非特恵(とっけい)原産地証明書」といい、輸入国側の法規制や取引先との契約条件、または信用状(L/C)の指定など、様々な目的に使用するための証明書類となっています。
もう一方は「 特定原産地証明書」といい、EPA(経済連携協定)における特恵税率を適用することを目的とする場合に申請する証明書類です。
-

-
参考特恵関税制度とは?概要と各税率の適用順位について
関税はたかが数%の違いでも ...
続きを見る
特定原産地証明書
特定原産地証明書には第一種と第二種があり、第一種は国によって定められた証明書の発給機関によって作成される(第三者証明制度)もので、第二種は各締約国の権限ある当局による認定(日本の場合は経済産業大臣)を受けた認定輸出者による自己証明(認定輸出者制度)によって作成するものとがあります。
なお、必要となる原産地証明書の種類はEPAの各協定ごとに異なるので、事前に利用するEPAに必要な証明書を確認した上で書類を取得するようにしましょう。
原産地証明書の取得手順
原産地証明書の取得手順は種類によって異なりますが、主に以下の流れに沿って進めます。
- 非特恵原産地証明書の場合
①発給機関への貿易登録
②申請書類の作成
③発給申請・受領
- 特定原産地証明書の場合
①貨物の関税分類番号(HS番号)の調査
②HS番号をもとにした税率の確認
③適用される原産地規則の特定
④発給機関への企業登録
⑤判定依頼
⑥発給申請・受領
詳しくは申請を行う各商工会議所などのWebサイトや、税関のWebサイトを参考するようにしましょう。
まとめ
今回は、原産地証明書の概要と取得手順するについてご説明しました。
原産地証明書は、貿易において重要な書類の一つであり、取引内容やL/C決済の要件、通関などの際に必要となるケースが多くあり、また用途に合わせて作成すべき証明書の種類も異なるので、事前に使用目的をしっかりと明確にし、理解することが大切です。
なお本記事は、あくまでも原産地証明書の概要の一部分をご紹介している内容となりますので、実際に書類を準備・申請する場合は、各商工会議所や管轄の税関に事前に相談をするようにしましょう。
物流に関するご質問またはご相談などはこちら
アスト中本では、国内外の貨物輸送やそれらに付随する業務を一貫して承っております。
また物流に関する身近なお悩みごとや対策についてのご相談も受け付けております。ご希望の場合は、以下のフォームまたはお電話にてお問い合わせください。
株式会社アスト中本 ロジスティクス営業部
〒556-0004
大阪府大阪市浪速区日本橋西1丁目2-5 Aiビル3階
TEL: 06-6633-0077



