日本から海外へ貨物を輸出する際の輸送方法は、物量や形態、納期などの様々な利用シーンに合わせて運送業者に依頼することになりますが、現在は物流サービスが発展・普及しているため、たとえ国内であってもその手段は様々です。
そこで今回の物流手帖では、 日本から海外へ貨物を輸送する方法についてご説明していきます。
※本記事は2023年10月時点の情報をもとに作成しています。
海上輸送とは

日本から海外へ貨物を輸出する際は、海上輸送や航空輸送、それらを組み合わせた国際複合輸送といった輸送方法を利用して貨物を輸送します。
海上輸送は、船舶を利用した輸送方法で、海上貨物と呼ばれることもあります。一度に大量の貨物を海外へ運ぶことができ、運賃も割安な点が最大のメリットです。
利用する船の種類
海上輸送で利用する船の種類は様々あり、形態もそれぞれ異なります。一般的に海上輸送で利用される船には、以下のような船があります。
①コンテナ船
船倉や甲板上に、貨物が入った実入りのコンテナを積載して輸送する船。
コンテナのサイズや形状は、ISO規格に基づいて標準化されているので、コンテナ船の作りもコンテナを輸送するために最適な構造になっています。
主に食料品や日用品、アパレル製品や雑貨など様々な貨物が輸送されています。
②ドライバルク船
鉄鉱石や石炭、木材などの資源や、小麦、大豆といった穀物類、塩など、様々な固体の原材料をバラ積み(梱包をせずに直接積み込む方法)で輸送する船。
輸送する貨物の種類や輸送量によって船のサイズや構造が変わります。
③タンカー
原油や石油精製品などの液体を輸送する船。
油槽船とも呼ばれています。
輸送する貨物の種類によってタイプや構造が異なり、それぞれに名称が付けられています。
石油を輸送するタンカーは、オイルタンカーと呼ばれています。
このように海上輸送で使用されている船には様々なタイプがあり、どの船も輸送する貨物に合わせた構造で設計されています。
一般的な貿易取引においては、貨物を効率的かつ安全に輸送するために考えられた輸送形態として、その殆どがコンテナ船によって輸送されています。
貨物が入った実入りのコンテナは、コンテナターミナルという特別な設備が備わった港でコンテナ船に積み込みますが、なかにはターミナルが備わっていない港もあります。
その場合は、コンテナ船が普及する以前に利用されていた定期船(在来船)で輸送が行われます。
在来船で輸送する貨物は様々で、一般的な貨物やコンテナに加えて、コンテナに収まりきらないサイズや重量の貨物も輸送されており、一部の船には荷役設備が備わった船もあります。
航空輸送のメリット、機体の種類について
航空輸送は、航空機を利用した輸送方法で、航空貨物と呼ばれることもあります。
航空輸送の最大のメリットは、何といっても輸送時間の短さにあります。
輸送時間が短いということは、それだけリスク回避の確率が上がるため、海上輸送とは大きく異なるメリットといえます。
航空輸送で利用する機体には、貨物専用機と旅客機があります。
貨物専用機はその名の通り、機体内部が貨物を積載するスペースになっており、一般の旅客機に比べて大量の貨物を航空輸送できる機体になっています。
貨物専用機は、一部のエリアに向けて限定された運行スケジュールが組まれており、旅客機に比べると便数も少ないため、旅客機の貨物スペースに入りきらないサイズの貨物や特殊な貨物が輸送され、なおかつ航空輸送で運ぶ必要がある場合などに利用されています。
旅客機の場合は、便数が多く、様々な国に向けて運行されているため、輸送手配を行う際のハードルは比較的低いといえます。
航空輸送で主に運ばれる貨物の種類
航空輸送で運ばれる貨物は様々ですが、一般的には電子機器や部品、季節商品や生鮮品、果物、製薬品などサイズが小さく、少量で高価な品物などが運ばれています。
またクーリエやEMSといった、ドア・ツー・ドア(発送地点から最終的な配達先まで貨物を届ける全ての費用が含まれた国際輸送サービス)のサービスでも航空輸送が利用されています。
クーリエやEMSの特徴は、運賃だけでなく通関費用なども含まれている点です。
国際複合輸送
国際複合輸送は国際複合一貫輸送ともいわれ、陸・海・空のうち少なくとも2種類以上の異なる輸送手段を利用して行われる輸送方法のことです。
フォワーダーや船会社などの複合運送人による一元管理のもとで、各区間ごとに輸送が行われます。
国際複合輸送のメリットとしては、単一の輸送ルートのみではなく様々な輸送ルートを選べる点や、発地から納品先まで一貫して輸送を行うことができる点などがあげられます。
また、荷主は単一の複合運送人と運送契約を結ぶだけで最終の目的地まで輸送ができるので、煩雑な事務関連の手続きや諸作業などの手間を省くことができます。
詳しくは以下の記事でもご説明していますので、ぜひご参考ください。
-
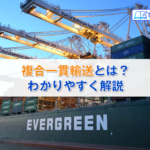
-
参考複合一貫輸送とは?わかりやすく解説
コンテナ輸送は、貨物を効 ...
続きを見る
まとめ
今回は、日本から海外へ貨物を輸送する方法についてご説明しました。
日本は島国のため、海外へ商品や物品を輸出する際は、必ず「海上輸送」もしくは「航空輸送」さらには「国際複合輸送」といった、3つの輸送方法で貨物を輸送することになりますが、どの方法にもメリットやデメリットがあり、輸送サービスの内容も各業者によって異なります。
急な場合を除いて納期まで時間に余裕がある場合は、どの輸送方法で運ぶべきなのかをしっかりと検討すると良いでしょう。
また各運送業者の手配や、必要な手続きなどを一貫して請け負ってくれるサービスもあるので、まずはフォワーダーなどの複合運送人に相談することもおすすめです。
物流に関するご質問またはご相談などはこちら
アスト中本では、国内外の貨物輸送やそれらに付随する業務を一貫して承っております。
また物流に関する身近なお悩みごとや対策についてのご相談も受け付けております。ご希望の場合は、以下のフォームまたはお電話にてお問い合わせください。
株式会社アスト中本 ロジスティクス営業部
〒556-0004
大阪府大阪市浪速区日本橋西1丁目2-5 Aiビル3階
TEL: 06-6633-0077



