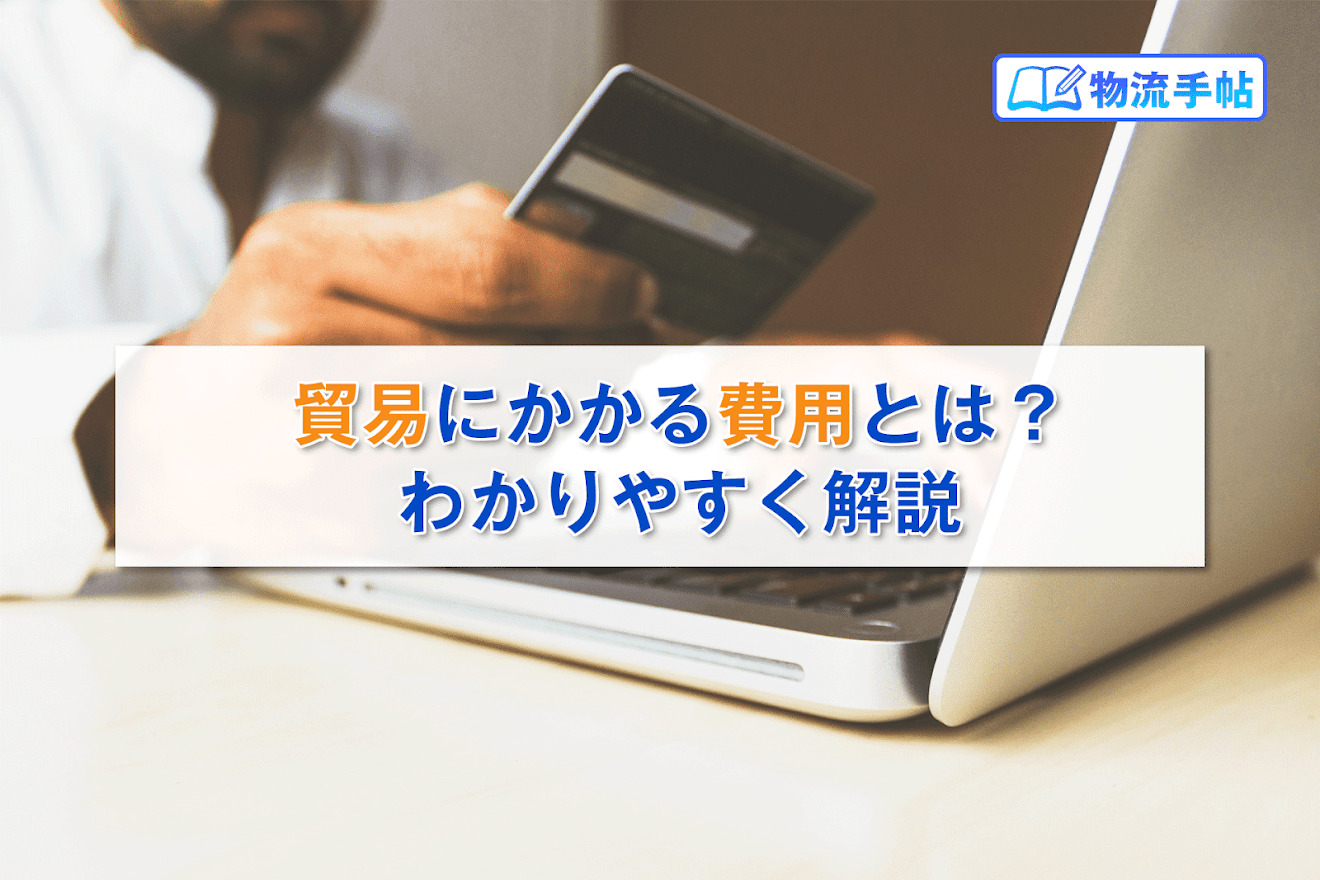最近の貿易形態はECサイトを利用して個人で行う場合から、従来の小~大規模な組織・企業などが行う場合まで様々な形態があります。
また、第三者を挟む三国間貿易や、仲介貿易などといった取引なども行われており、貿易形態は多様化しつつあります。
物流手帖でも、貿易の取引の流れや物流業者の役割、三国間貿易などについて記事にしてきましたが、なかでも非常に重要な項目となる貿易にかかる費用は、具体的にどのようなものがあるのでしょうか。
今回の物流手帖では『貿易にかかる費用』の概要と種類(一部)についてご紹介していきます。
※本記事は2023年7月時点の情報をもとに作成しています。
貿易にかかる費用とは?

貿易とは自国と他国との間で行われる商品の売買やサービスの提供などの取引のことを指しますが、通常の国内で行う商取引と違って、費用の種類や金額も大きく異なります。
例えば、単純に物理的な距離が伸びるため、輸送にかかる費用が国内の取引に比べると増加する点です。
そのほかにも、税金や法令にかかる費用、貨物の積み卸しにかかる費用や保険料など様々な費用があります。
輸出時にかかる費用
国内で商品を販売する際の価格設定を単純化してみた際に、考えられる費用としては「商品にかかる代金」と「送料」が挙げられますが、輸出の場合は国内でかかる送料とは別に「国際輸送運賃」と「運賃以外で輸出貨物にかかる費用」がかかることになります。
また外貨で取引をする場合の為替変動や取引先からの代金回収にかかる信用調査、政治的・経済的な事情の変化などの「リスクにかかる費用」なども場合によっては含む必要があります。
国際輸送運賃
国際輸送運賃は、ただ単に距離イコール費用というわけではなく、貨物の種類や輸送手段、また輸送におけるリードタイム、輸送する時期などの様々な条件によって価格が変動します。
なお、状況に応じてどのような手段で国際輸送を行うべきかを選定したり、先導して段取りを行う業者のことをフォワーダー(フレイト・フォワーダー)といいます。
運賃以外で輸出貨物にかかる費用は、「通関費用」や「税関検査費用」、荷役の際に必要となる「貨物の積み卸しにかかる費用」、コンテナ輸送の場合は「バンニングにかかる費用」、貨物そのものや国際輸送にかける保険料」、原産地証明を取得する場合には「必要書類を手配する費用」などが挙げられます。
輸入時にかかる費用
輸入の場合も通常の国内取引と同様に「商品代金」と「送料」に加えて、輸出時にかかる費用と同じく国際輸送運賃やその他の諸々の費用が発生しますが、輸出時ともっとも異なる点は「関税」と「消費税」です。
関税は、輸入する品物や取引内容によって金額が変動します。
なお、ここでいう取引内容とは、個人輸入なのか少額輸入なのか、それとも商業輸入なのかを指しています。
消費税は、たとえ海外の品物であっても日本で消費するためのものであれば、必ず発生する税金となります。
ちなみに、他国に輸出するための仕入れ目的として輸入した貨物の場合は、仕入れ時に支払った消費税の還付を受けることができるので、詳しくは税務署などで確認するようにしましょう。
他法令について
輸出・輸入どちらの場合にも該当する費用の例として、ほかには「他法令の許可申請および承認にかかる費用」があります。
他法令とは、輸出または輸入する際に税関以外の各省庁の許可・承認が必要な貨物を定めた法令で、知らずに輸入して貨物は到着しているけれど港から引き取りが出来ないといったケースも稀にあるので注意が必要です。
まとめ
今回は、貿易にかかる費用の概要と種類(一部)についてご紹介しました。
実際に取引を行う際は、一般的に国際的な貿易の指標となるルール(インコタームズ)に沿って、売り手と買い手のどちらがどこまで費用負担をするのか、交渉・決定されます。
取引条件の交渉を行う際は、その貿易にどのような費用が発生するのか、あらかじめ理解しておくことが大切です。
また、金銭の受け渡しを行う際の決済方法やお金の流れについても、事前に取引先とすり合わせを行い、リスク管理を徹底することも重要になってきます。
貿易における決済方法やお金の流れについては、以下の記事で詳しくご紹介していますので、ぜひご覧ください。
-

-
参考L/C決済の流れ、貿易における決済方法について
海外の取引先と貿易を行う& ...
続きを見る
物流に関するご質問またはご相談などはこちら
アスト中本では、国内外の貨物輸送やそれらに付随する業務を一貫して承っております。
また物流に関する身近なお悩みごとや対策についてのご相談も受け付けております。ご希望の場合は、以下のフォームまたはお電話にてお問い合わせください。
株式会社アスト中本 ロジスティクス営業部
〒556-0004
大阪府大阪市浪速区日本橋西1丁目2-5 Aiビル3階
TEL: 06-6633-0077