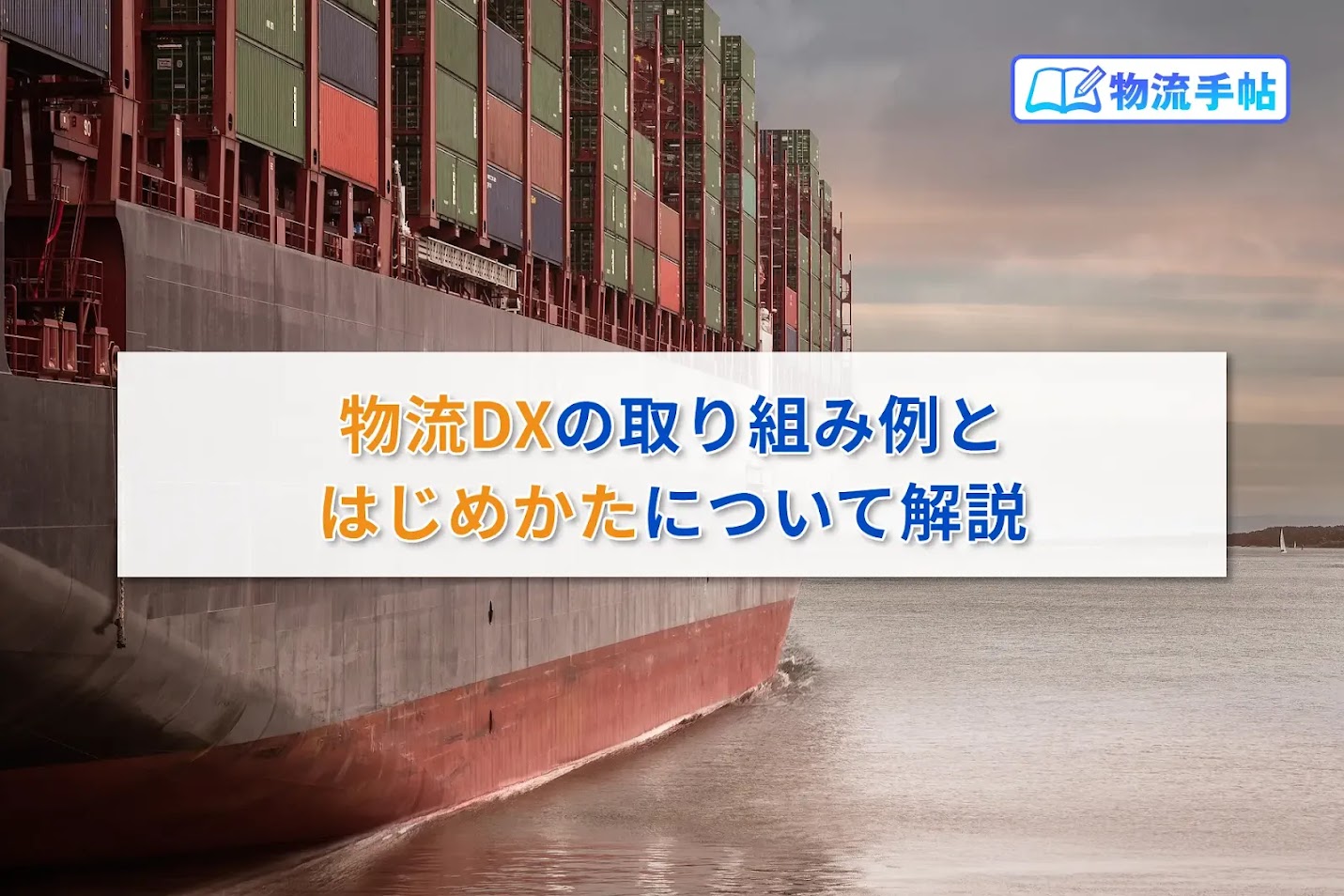現在、様々な業界で推進されている、DX(デジタルトランスフォーメーション)は、これからの物流を考えていく上で欠かすことのできない重要なキーワードの一つです。
今回の物流手帖では、物流DXの考え方や取り組み例、物流DXのはじめかたについてご説明していきます。
※本記事は2025年7月時点の情報をもとに作成しています。
物流DXとは

物流DXとは、デジタル技術を活用して物流のあり方を根本から変革し、新たな価値を生み出すことを指します。
現在の物流業界は、昨年話題となった「物流の2024年問題」で懸念された人手不足やドライバーの高齢化、EC市場の拡大に伴う小口配送の増加、そして非効率な業務プロセスや燃料費の高騰など、数多くの課題に直面しています。
これらの課題を解決する有効な手段として、デジタル化やデジタル技術の導入が効果的であり、それらを連携・活用し、業務プロセスや物流ビジネスの構造を根本から変革していくことが、物流DXの本質です。
物流DXの取り組み例
物流DXは、倉庫、輸送、配送、そしてバックオフィス業務まで、物流のあらゆるプロセスに変革と革新をもたらすと考えられています。
ここでは、物流DXを推進することで得られる様々なメリットを、具体的な取り組み例とともにご紹介します。
1:倉庫業務の効率化
倉庫管理システム(WMS)の導入により、リアルタイムで在庫状況を正確に把握し、入出庫の管理を効率化することができます。これにより、在庫の過不足を防ぎ、ピッキング作業の最適化や棚卸しの効率化にも貢献します。
2:ロボットやAGV(無人搬送車)の活用
重量物の搬送や、特定のルートでのピッキング作業などを自動化することができます。これにより、人手不足を解消しつつ、24時間稼働も可能になるため、作業効率と生産性が飛躍的に向上します。
3:AIによる需要予測
過去の販売データや気象情報、イベント情報などをAIで分析することで、より具体的かつ正確な需要予測に繋げることができます。これにより、最適な在庫量を維持することができ、過剰在庫によるコスト増や欠品による販売機会損失を防ぐことができます。
4:配送ルートの最適化
GPSで車両の位置情報をリアルタイムで把握し、渋滞情報や配送先の状況を考慮した、最適な配送ルートをシステムが提示することで、走行距離の短縮、燃料費の削減、そしてドライバーの労働時間の改善に大きく貢献します。
5:ドローンや自動配送ロボットによるラストワンマイル配送
過疎地域や、限定されたエリア(大学構内、大規模商業施設など)でのラストワンマイル配送において、ドローンや小型の自動配送ロボットの活用が進んでいます。人手不足の解消だけでなく、配送コストの削減にも期待できます。
6:バックオフィス業務のデジタル化
紙ベースの請求書や契約書をデジタル化することで、印刷・郵送コストの削減、業務のスピードアップ、保管スペースの削減を実現します。また、ペーパーレス化は環境負荷低減にも繋がります。
7:勤怠管理・運行管理システムの導入
システムの導入により、ドライバーの労働時間や休憩時間を正確に管理することができます。また運行記録もデジタル化することで、より効率的で安全な運行管理が可能になります。
8:サプライチェーン全体の連携強化
荷主、運送会社、倉庫業者、港湾事業者など、サプライチェーンに関わる企業間で、データをリアルタイムに共有・連携する基盤を構築します。これにより、情報伝達の遅延やミスをなくし、サプライチェーン全体の可視化と最適化を図ることができます。
このように物流DXを推進することで、業界が抱える様々な課題の解決に役立ち、さらにサービスの拡充や柔軟性の向上を通じて、企業の競争力強化に繋げることができます。
物流DXのはじめかた
物流DXの取り組み例でご紹介したように、デジタル技術を駆使したDX推進は、より良い環境や仕組みを構築し、従来のワークフローを新しいシステムへと変革することで、様々な効果をもたらします。
その変革の規模や範囲は、まず自社の事業規模に合わせて検討することが第一歩になります。
以前の記事でもご紹介しましたが、当社のグループ企業である、ASUTO GLOBAL LOGISTICS (Thailand) CO., LTD.(AGLT社)では、現場で働く作業員にとって使いやすく、なおかつヒューマンエラーを改善するためのシステムを組み込んだ倉庫管理システム(WMS)を開発・導入しています。
このシステムを開発する際に注目したのは、実際の現場で、どの段階でミスが起きていて、どのような状況でミスが起こりやすいのかを徹底的に検証した点です。その上で、システムの企画から開発・導入までを行いました。
このように、DXに取り組む際には、何を改善し変革すべきなのかを明確にし、現在の問題点の洗い出しや課題を見つけることから始めることが重要です。それが、物流DX推進の第一歩に役立つアイデアを生み出すことに繋がります。
まとめ
今回は、物流DXの考え方や取り組み例、物流DXのはじめかたについてご説明しました。
新しい技術やシステムを導入する際は、現場の作業員の理解と導入後のサポートを徹底し、意見を取り入れながら進めることで、スムーズな導入と定着を図ることができ、社内の知見と経験を積み重ねることができます。
関連記事として、以下の記事では、物流DX推進の背景やDXの概念、実現のためのポイントについて解説していますので、ぜひご覧ください。
-

-
参考物流DXとは?物流DX推進の背景から考える実現のためのポイント
昨今、物流業界では、2024年問題や2025年4月から新たに施行が始まった改正物流効率化法など、物流の効率化を図る取り組みが活発化しています。物流DXもそのうちの一つとして、現在も注目されています。 ...
続きを見る
物流に関するご質問またはご相談などはこちら
アスト中本では、国内外の貨物輸送をはじめ輸出入に関わる業務を一貫して承っております。
また物流に関する身近なお悩みごとや改善・対策についてのご相談も受け付けております。
お問い合わせは、以下の連絡先にお電話いただくか当サイトのお問い合わせフォームから
ご連絡ください。
株式会社アスト中本 ロジスティクス営業部
〒556-0004
大阪府大阪市浪速区日本橋西1丁目2-5 Aiビル3階
TEL: 06-6633-0077